|
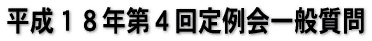 |
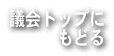 |
|
|
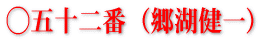 私はみらい仙台の郷湖健一です。議長から発言のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 私はみらい仙台の郷湖健一です。議長から発言のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。
我が仙台市も、新しい梅原市長を迎えはや一年五カ月を迎えております。市長は、就任当初より、仙台を安心・安全なまちづくりを基本に、日本一住みやすい都市の創設を基本に当初より東奔西走し、海外にも幾度となく訪問し仙台を売り込むシティセールスに熱心でありました。しかし、理解をいただけない市民からは「こんな厳しい財政事情の中で、市長は税金を使い海外にばかり行っている」と批判される一こまがございましたが、しかし、しかと説明をされれば市民もわかっていただけることと私は思うのであります。
要するに、市民に対し市長の説明責任が足りなかったのではないかと思うし、私は、国内の都市間競争はもちろん、グローバル社会の中で世界各国との経済交流は大変大事なことだと私は思うのであります。梅原市長はまさに国際人であり、諸外国とのかかわり、外国要人とのかかわりも深く、そして、直接英語で自分の言葉を相手に伝えられる市長は数少ないと思います。これからも大いなる期待を寄せるものであります。
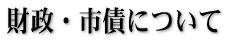
そこで、質問の本題に入りますが、本市財政について質問をさせていただきます。
市税収入は平成九年度を最高に年々減り続け、平成十七年度決算でやっと前年度を上回ったということであります。私もやっと景気回復の兆しが見えてきたのかなと期待をいたしておるところでありますが、梅原市長が就任し、当市の財政状況をごらんになり、精査をいたしてどのように仙台市の財政を感じ取ったのか、市長の率直なお考えをお聞きいたしたいのであります。
また、「入るを量りて出ずるを為す」、経済の基本でありますが、昨今の大変厳しい行財政の中にあっては、特に「入るを広げて出ずるを制する」ことが肝要であります。少子高齢化の中、ますます行政需要が増大する中で、むだを省く取り組みが必要であります。市長を初め幹部の方々、一般職の方々、市議会、町内会を初め各種団体等も含めた多くの方々に御理解と御協力をいただきながら、財政の健全化に取り組んでいることをもっともっと市民にわかりやすく市民の理解をいただくよう、あらゆる機会、メディアを通じて市民に理解をいただく努力をすべきと考えますが、市長の御所見をお願いいたします。
そして、都市の成熟度、人口減少化、少子化、高齢化の進行等ますます行政需要が増大する中で、また、政府の行革の中で政府からの予算の流れが細まり、今、まさに行政に求められることは健全財政化の確立だと私は思いますが、いかがでしょうか。
本市財政を見ますと、平成十七年度決算ベースで、一般会計で七千三百三十三億一千四百万円の借金を抱えることとなります。また、特別会計が約六百四十億五千四百万円余、さらには各企業会計も設備投資等の累積赤字を抱えながらの経営であり、企業会計五千八百六十三億九千四百万円となり、まさに膨大な借金であります。
これらの市債残高を合計いたしますと、まさに一兆三千八百三十七億六千二百万円余となります。まさに大変な大きな額となり、市民一人当たりの借金は約百三十九万円となり、民間企業であれば既に倒産であり、我々議会人も襟を正して取り組まなければならない最重要課題であります。
実質公債比率は一八・九%だから、あるいは、政令市の中で順位は高い方から七位だからと甘えは許されません。さらに、宮城県財政も加えますと相当な額になります。
一方、国の財政に目を向けますと、借金も八百兆円余りとも言われ、まさに借金王国であります。国民一人当たりに換算すると六百万円余となるわけでありまして、まさに気の遠くなるような額面であります。そのような状況の中で、大きく国に頼ることもできず、地方財政もより厳しくなることは受け合いであります。今、対策、手を打たなければと私は危惧するものであります。
今、地方自治体の四分の一が財政難にあえいでいると言われております。来年四月から赤字再建団体に指定され、国の管理下に置かれる人口一万三千人の夕張市が、六百三十億円の借金を抱え財政破綻いたしました。この自治体を見るにつけ、住民負担は最大平均で十六万円の負担増、学校の統廃合、保育所、幼稚園の見直し、老人ホームの廃止、病院の廃止、職員幹部の方々の給与等の大幅削減も、また職員の大幅削減、このことにより人口の流出や商店街の衰退も懸念されるなど、惨たんたる状況であります。
以上申し上げましたとおり、我が仙台市はそのようなことにはならないと信じますが、体力の残っているときから健全財政に取り組み、仙台市の持続的発展を期待するものであります。今後の財政健全化に取り組む手法、収入を高める手法に取り組む方法があればお尋ねいたし、梅原市長の手腕に期待するとともに、我々議会も職員も一つになって取り組まなければならないと存じます。市長の御所見、取り組む決意のほどをお尋ねいたします。
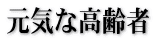
次に、元気な高齢者が生き生きと活躍できる福祉社会のあり方についてであります。
我が国は、世界に類のない速さで高齢化社会に移行しております。また、戦後間もない生まれの団塊の世代が退職を迎えます。平成二十七年前後には高齢人口が全世帯の二五%を超え、四人に一人は高齢者となります。我が仙台市も年々その比率を高めている状況であります。
急速な高齢化は、医療、福祉、年金等の高負担を必要とし、また、社会全体の活力があるうちに、人生八十年代時代にふさわしい社会システムの形成が急務となっております。そのため、健康福祉教育など総合的に高齢者対策を講じ、生き生きとしたゆとりのある高齢者社会を構築してまいらなければならないと私は思うのであります。しかし、いまだ高齢者は余生などとする固定観念や、高齢者を一律に年齢で弱者扱いする習慣がまだ多く残っていることは大変残念であります。
また、日本の老人人口の多くの方々は健康で、何らかの形で社会貢献したいと健康なお年寄りは願っているのであります。したがって、活力ある社会を築くためには、今後ますます増加する元気な高齢者には社会参加をいただき、活力を支えていただくことが、また、その対策がますます重要になってまいります。
しかし、現代社会においては、まだ元気な高齢者の知識や体験が十分に活用されていないことであります。サラリーマンで退職された方々は豊かな知識や経験をお持ちの方々も多く、相談窓口等が不十分なことから、高齢者の社会参加では本人の希望に十分に応じられないのが現実であります。
また、高齢者に社会参加を促すのであれば、エレベーターやエスカレーター等の整備は進んでおりますが、舗道等の面的整備も大分進んではいるが、まだ十分とは言えず、バリアフリーのさらなる推進が求められます。また、元気なお年寄りを育成することは医療費の軽減にもつながり、大事なことであります。軽スポーツ等々、体を動かす施設等の整備も必要であります。
以上述べましたが、高齢者の活躍する社会は、経済や社会を活性化させるとともに、現役世代のさまざまな社会保障等の負担軽減にも通じるものと考えます。このような社会を実現していくための今後の取り組みについて御所見をお尋ねしたいのであります。
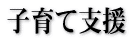
次に、少子社会に対応した子育て支援のあり方に関してであります。
全国の合計特殊出生率は年々その値を下げ続け、とまることのない状況であります。少子化の進行は、子供自身の自主性や社会性を低下させるばかりでなく、社会保障費用の過重な負担や労働の減少等々、経済社会の活力の低下を招くおそれがあります。
いかに少子化といえ、子供を産む産まないは国民一人一人の意識や価値観と深く結びついており、行政が強制することはできないのであります。しかし、社会の仕組みを、子供を持ちたい人が安心して子育てできるものに変えることは可能であります。それには、行政のみならず住民、企業など社会のすべての力を結集し、子育てを社会的に支援する仕組みづくりに取り組み、少子社会の備えに万全を期す必要があります。
以上述べましたとおり、少子化の要因は著しい晩婚化と未婚率の上昇であると言われております。要は、現代社会は、実際には子育てに対する親の心理的・精神的負担の増大であり、住民同士の連帯感が薄れ、一人悩むことが多いのであります。また、現在の親自身の多くが核家族の中で成長し、身近な子育ての現場に接する機会、経験に乏しく、こうした状況は今頻繁に起きている幼児・児童虐待、いじめを生む要因とも考えられること、また、子育てに伴う経済的負担が余りにも大きいことであります。また、都市では教育費など子育て家庭にかかわる支出が多く、親の負担を一層大きくいたしております。
今申し上げましたような障壁を取り除き、子供を産み育てる環境整備を、あるいは子供を産み育てる親たちの自主研さんを促進するような機会をつくることも大事なことであります。ただ単にすべての行政に負担を求めることを改め、住民と企業、社会が一体となり、市民全体にて支える仕組みを整備することが最も大事なことだと思います。
以上いろいろと述べさせていただきましたが、これから先も少子化は続くと思いますが、二十一世紀の少子社会を迎えても、安心して子供を産み育て、子供が健やかに成長できる社会を築くことは国民共通の願いであります。そのためには、時を逸することなく社会的な子育て支援の仕組みをつくり上げなければならないと存じます。行政、民間、社会ともども、先導的かつ多様な子育て支援の構築になお一層全力を傾注し取り組むべきと考えますが、現在の取り組み、または何らかの新しい施策をお考えであればお示しいただきたいのであります。
これをもって私の一般質問といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
|
|
|
|
|
|
 ただいまの郷湖健一議員の御質問にお答えを申し上げます。 ただいまの郷湖健一議員の御質問にお答えを申し上げます。
仙台市の財政状況についての御質問にまずお答えを申し上げます。
税収の大幅な落ち込み、もちろんその背景にはバブル崩壊以降の長期間にわたる景気の低迷が長引いたことがございます。そして、少子高齢化が進展していること、それに伴う扶助費が増大し、依然として公債費が高水準にある等々、義務的な経費の構成比が高まっております。財政の硬直化が残念ながら相当程度進展しているわけでありまして、現時点において依然として極めて厳しい財政状況であるという認識をしております。
しかしながら、言うまでもなく、仙台市民の現在ないし将来の幸福のために、仙台市の発展のために、必要な投資はタイムリーに、あるいは早目早目にやっていかなければならない。そのために、まちの発展のためのいわゆる都市インフラの整備については、とりわけ重点的に投資を進めていかなければならないことは論をまたないところであります。代表的なものはもちろん地下鉄の東西線の加速的推進でございます。あるいは上下水道、道路といった公共インフラの整備も引き続き可能な限り積極的に進めていきたいと思っております。
そして、何よりも短期的な対策はいろいろなものを講じているわけでございまして、収入増についての取り組み、一部に成果が出始めてはおりますが、常日ごろ申し上げますように、最も王道といいますか、効果的な施策は、言うまでもなく仙台自体の経済、産業、中小企業、商店街、ありとあらゆる面における活力を活性化し、そのためには仙台の外から活力を呼び込む、そして仙台に本来内在している活力、あるいは現に発揮している活力との間でプラスの相互作用をつくり出し、そして新しい付加価値を生み出し、それが、事業者、個人の所得を増加する、市民の懐が潤う、それによって仙台市の財政が潤うと、こういう好循環モデルをつくらなければならないわけでございます。
そのためにまた必要な手段、あるいは投資が必要でございます。国内外からの研究機関の誘致なり観光客の誘致なり、そのためにはまた仙台のさまざまなインフラ整備が必要である。常にある意味ではニワトリと卵の関係にございます。研究機関を誘致するためには、その子女の教育のために教育環境の整備が図られなければなりません。初等・中等教育の再生あるいは立て直しも喫緊の課題でございます。
このようにある意味ですべては連関しているわけでございますが、要すれば、仙台市民の幸せを求めてさまざまな施策を講ずること、そのためにはもちろん十分な財源が必要であること、そのためには経済を活性化する、そのために必要な投資を早目に行うこと、これが基本であろうかと存じます。
次に、少子高齢化社会という議論の中で、高齢者が活躍できる社会の実現、あるいは少子化に対応した子育て支援のあり方についてのお尋ねがございました。
詳しくは関係局長から御答弁申し上げますが、私から一言申し上げれば、間違いなく高齢者の方々、シニアの方々になお一層元気に頑張っていただき、地域のために御貢献いただくことが大変に期待されておりますし、また、行政として、そのための基盤の整備、環境を整えることなどいろいろな積極的な支援を行ってまいりたいと思っております。詳しくは健康福祉局長から御答弁申し上げます。
と同時に、やはり子育て支援のあり方、これが非常に重要な課題であることは常々申し上げているとおりでございまして、子供未来局長以下、この夏以来、相当程度広範囲に子育ての現場に出かけまして、保護者の方々、あるいはいろいろなボランティアの方々から詳細なヒアリングをし、現在、その成果に基づいた問題意識の整理、とりわけ子育ての孤立化が深刻な事態に至っております。こういった観点から、現在、十九年度の予算編成の過程にこの夏以来の作業の結果を集約し、政策の最終的な詰めを行っているところでございます。
行政と市民の皆様あるいは事業者の皆様が互いに連携して協力し合って、仙台のコミュニティー全体として子供さんを育てやすい環境をつくっていくことに引き続き努めてまいりたいと思います。
詳細にわたります部分は、関係の局長から答弁をさせたいと存じます。
以上でございます。
|
|
|
|
|
|
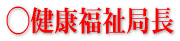 (瀬戸和良)高齢者が活躍できる社会についての御質問にお答え申し上げます。 (瀬戸和良)高齢者が活躍できる社会についての御質問にお答え申し上げます。
議員の御指摘ございましたように、高齢社会を活力あるものにするためには、バリアフリーのさらなる推進を初め、高齢者が社会参加しやすい環境を整え、高齢者の方々の知識や経験を地域の資源として生かしていくことが大変重要であると認識しております。
また、高齢者の社会参加は、高齢者自身の生きがいづくり、さらには健康寿命の延伸にも通じるものと考えておりまして、本市といたしましても、高齢者保健福祉計画の趣旨に基づき、シルバー人材センターにおける就労支援を初め、仙台市ボランティアセンターでの活動相談や各種団体への助成などを通じ積極的に支援を行ってきたところでございます。
今後とも、相談機能の充実強化なども視野に入れ、元気な高齢者がそれぞれの意欲や希望に応じ生き生きと活躍できるきめ細かな体制づくりを、関係各局と連携しながら着実に進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
|
|
|
|
|
|
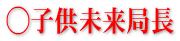 (荒井崇)私からは少子化社会に対応した子育て支援のあり方についての御質問にお答え申し上げます。 (荒井崇)私からは少子化社会に対応した子育て支援のあり方についての御質問にお答え申し上げます。
急速な少子化が進む今日、議員御指摘のとおり、行政のみならず、地域住民の方々、企業など幅広い主体の参画によりまして、社会全体として子育てを支援する仕組みを築いていくことが必要であると認識いたしております。
本市におきましては、現在、平成十七年に策定いたしました仙台市すこやか子育てプラン第三期行動計画に基づきまして、子育て支援施策を実施しておるところでございますけれども、近年の急激な少子化の進行に対応するため、現在、市長から御答弁申し上げましたように、来年度以降、速やかに重点的かつ優先的に取り組むべき施策ですとか新たな施策につきまして、子育ての孤立化を防ぐ地域支援、また働き方の見直しの観点からの仕事と子育ての両立支援、経済的支援などを重視すべき課題といたしまして、具体的な施策の調整を図ってきているところでございます。
今後とも、少子化社会に対応いたしました各種の施策の充実に努めてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
|
|
|
|
|